COMMENT

1950〜60年代を代表する写真家といえばロバート・フランクとダイアン・アーバスだが、ヴィヴィアン・マイヤーの才能は彼らに匹敵する。あらゆる写真家が目標とし、嫉妬するほどの実力の持ち主だ。野心家であり、努力家であり、チャレンジ精神の塊だったが、あらゆるものを公平に見ようとする無私の眼差しを備えていた。彼女自身もそのことを充分にわかっていたはずなのに、なぜ生前に自作を発表しなかったのか。謎としかいいようがない。まさに20世紀の写真史を書き換える”発見”といってよいだろう。
飯沢耕太郎(写真評論家)
「オークションにより発見」された「謎の写真家」の情報は調べても出てこず、やっと手がかりを見つけた時には「直前に亡くなっていた」という人物像に迫るこの映画は、写真というものの価値をよく表している。「写真」は常になんらかの「物語」を孕み、それを読み取られることで受容されていく。ヴィヴィアンさんの残した謎に思いを馳せることこそ、この写真家の価値なのではないだろうか。そして映画が進むにつれ、その謎は少しずつ解き明かされていく。映画が終わりいくつかの答えを知った後、観客はその写真の見え方が少し変化していることに気づくのである。
高橋宗正(写真家)
アメリカは広い、そして深い孤独を抱えている。埋もれた写真家奇跡の復活劇かと思っていたら、この国にぽっかり空いた底なしの穴を覗き込むような優れたドキュメンタリー映画だった。
鷹野隆大(写真家)
ヴィヴィアンの情熱は、対象とひとつになる快感を求めてストリートをハンティングすることにのみ費やされた。ファインダーを覗いたとたんに喧噪は遠のき、「見る人」になれる。そのときの充足した孤独ほど、素晴らしいものはなかったにちがいない。
大竹昭子(作家)

もし、だったら、という事は無いと言われている。全て必然という事か、ヴィヴィアン の場合、並々ならぬ彼女の才能と写真の力が爆発するように地下から噴出したようだ、本人が望む、望まざるに関わらず。そして、起爆剤 になった人の縁と拡がっていくつながり、これを奇跡というのだろう。
広川泰士(写真家)
ヴィヴィアン・マイヤーという「女版ウィリアム・エグルストン」の発見は、写真界にとっては価値ある恐竜の化石の発掘と同じだ!! Walla!! アート、写真、ミステリー好きにはマストな映画!!
ルーカスB.B.(PAPERSKY編集長)
アジェもラルティーグも。写真の歴史は常に「発見」に彩られている。しかし、ヴィヴィアン・マイヤーほど奇跡的で感動的な発見のされ方はなかった。今はただただ彼女の撮った写真が見たい。
鈴木芳雄(美術ジャーナリスト)
世の中には、隠され、忘れられて、放置されている、もの スゴく良い写真がイッパイあるんです。そしてそれらの写真は発見されるのを待っています。あたなの周りにもヴィヴィアン・マイヤーはいるかもしれません。
ホンマタカシ(写真家)
まるで恐竜のような巨人的写真家だーーー
写真を撮ることで癒される人たちは世の中にたくさんいる。しかし彼女のように才能ある人は稀だ。しかしもっと奇跡的なのは僕たちがその膨大な量の素晴らしい写真や動画、そしてヴィヴィアンに直接関わった人たちの話までもがまとめて見られることだ。撮影者、発見者、そして思い出を語る者たち。今でもアメリカは滑稽で、魅力ある国だと思った。
若木信吾(写真家)
マイヤーは写真を公開したかったかなんて愚問。他人の心に触れる方法も、その瞬間をカメラが記録できることもなぜか知ってて、世界と繋がろうとしてたんだから。同じくシカゴで発見されたダーガーとはそこが異なる。
保坂健二朗(東京国立近代美術館主任研究員)

ストリート・フォトグラファーというのは対する人との心の距離感が一種独特な立場にある。被写体の本質や、背負った人生の哀歌を一瞬でつかみ得るほど近しい距離にいたかと思えば、その実、その人の名前すら知らなかったりする。稀いなる才能に恵まれたストリート・フォトグラファーの彼女は幸せだったのか、果たしてそうではなかったのか。答えはこのドキュメントの中にある。
シトウレイ(ストリート・フォトグラファー)
撮り続けることでしか世界と繋がれなかった、そんな彼女の孤独に寄り添えたのはカメラだけだったのだろう。作品を発表することでなにかが変わることが怖かったのかもしれないが、それはもういまとなってはわかりようのないことだ。死後発表された膨大な数の写真だけが、静かに彼女の怒り、孤独、生への執着を物語っている。
川内倫子(写真家)
彼女の佇まい、態度、生き様、そして写真からは、人間の業(ごう)の肯定と、生への欲望が滲み出ている!!!!!!!!
宇川直宏(”現在”美術家 / DOMMUNE)
これほど観る人の心を揺さぶる写真を生涯発表しようとしなかった無名のヴィヴィアン・マイヤー。この謎の人物に迫るドキュメンタリーは必見です。
ピーター・バラカン
アメリカがもっとも自信にあふれていたはずの時代に、眩しさの裏側に張りついていた影。それをヴィヴィアン・マイヤーは本能的に肌で感じとっていて、その距離感のようなものが、見るもののこころをざわつかせるのだろう。
都築響一(写真家、編集者)
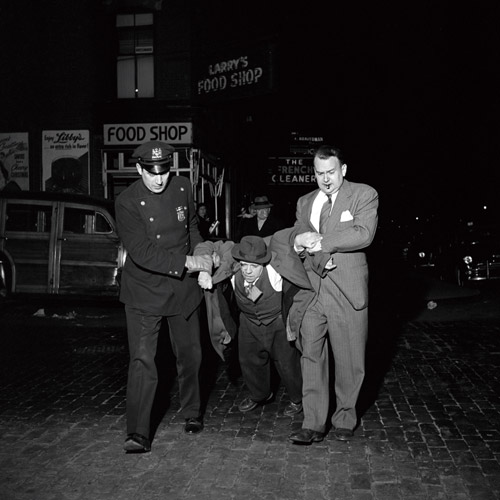
大きな謎を残しながら、それでも観る人が感動を覚えるのは、やはりこの作品がミステリーではなくドキュメンタリーだからだ。もっと言ってしまえば、これがヴィヴィアン・マイヤーを巡るドキュメンタリーであると同時に、視点を変えればジョン・マルーフの個人的なドキュメンタリーでもあるからだろう。
門間雄介(編集者/ライター)
乳母という身分とひきかえに写真を撮る自由を手に入れ、孤独とひきかえに卓越した洞察力を手にしたヴィヴィアン・マイヤー。彼女の才能の源泉は、病的なまでの蒐集癖にあったと思う。新聞記事やガラクタを集めたのと同じように、街を、道行く人を、路上で起きるドラマをひたすらカメラで蒐集することに没頭した生涯。撮ることに執着しながらも、一度も現像されることのなかった膨大なフィルム群がその情熱のいびつさを物語っている。偶然の発見によって、素晴らしい才能の恩恵にあずかれた幸運に感謝します。
太田陸子(「IMA」エディトリアルディレクター)
ファウンド・フォトとして発掘されたヴィヴィアン・マイヤー。ゴミ同然と思われていたネガは、発掘者の審美眼と行動力によって人々を感動させるアートへと昇華した。世界中の人が様々な時代の中で撮影した写真には、まだ見ぬ秘められた可能性が眠っているかもしれない。これからはただの「写真」と侮ってはいけない。
番場文章(代官山 蔦屋書店 写真・アートコンシェルジュ)
未知の「写真家」が発見される興奮と、発見された「写真家」に見え隠れする狂気。女性としての哀しみこそが、彼女を突き抜けた「写真家」にしているのではないでしょうか。
森岡督行(森岡書店)
写真が素晴らしいのはもちろんだが、その遺留品、証言から浮き彫りにされてくる彼女自身の素顔がミステリアスにして魅力的!それと同時にマイヤーを発見しただけでなく、世に知らしめた監督のセンスと執念も大発見!
長谷川朗(ヴィレッジヴァンガード下北沢 次長)
才能と孤独と新聞の山に埋もれたひとりの女性が、ひとりの酔狂な青年の執念によって発見され写真史に名を刻む(?)までの、奇跡のドキュメンタリー。カメラとテレコが相棒だった記録魔の変人を、「有名人になりたくなかったアンディ・ウォーホル」と呼ぶのはどちらかに失礼だろうか?いまも世界中にInstagramでシェアされない膨大な名作が、蚤の市からiPhoneの中まであらゆる場所に眠っているのだと想像して、勝手にワクワクした。ああ、天才を見つけたい!
内沼晋太郎(本屋B&B/ブック・コーディネーター/クリエイティブ・ディレクター)

人は誰もがいくつもの顔を持って生きている。ヴィヴィアン・マイヤー、彼女のことを知りたければ、彼女が生涯を捧げた膨大な量の作品を、見ること。天才?奇人?写真家?乳母?肩書は最早どうでもよく、ただ単純に、彼女が撮った写真は素晴らしい。
永井雅也(IMA CONCEPT STORE)
語りえぬものについてヴィヴィアンは写真で向き合っていた。彼女にとってシャッターを押す行為は、世界を発見し、意味を与える行為だったのだろう。偉大な仕事を成しえる人たちは、職種に関係なく世界の奥深くにある同じ場所を見つめている。ヴィヴィアンも、その世界に達することができた、偉大な写真家であるのは間違いない。
中島祐介(アートブックショップ[POST]ディレクター)
(順不同・敬称略)
